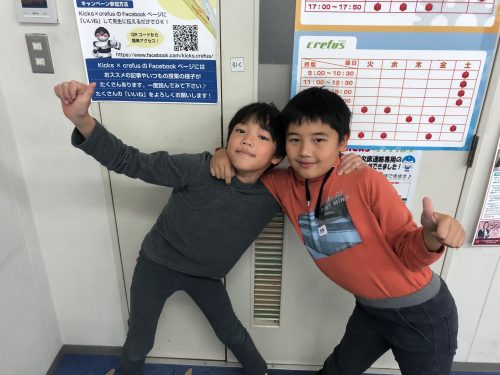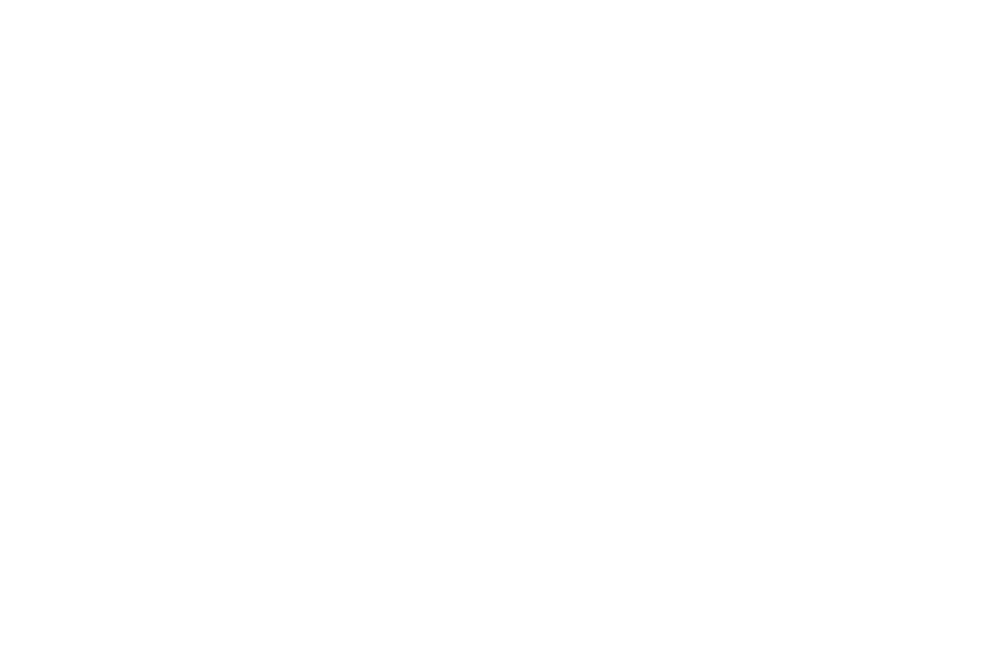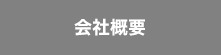多様化する中学入試!その共通点とは?

今まで中学受験と言えば国算理社の4教科、もしくは国算の2教科で、小学5年生までには塾等で学校の履修内容を済ませておき受験対策に入っていく…このような流れが一般的でした。今も主流ではありますが、しかしここ数年、私立校を中心に入試の形態は確実に変化しています。
公立の中高一貫校出現により、単純な知識量ではなく、複数の教科をまたいで知識を組み合わせ課題の答えを導く「適性検査」選抜が行われるようになります。それに追随する形で私立校が適性検査を導入し、それが「独自入試」という形で様々に広がりを見せました。導入校の増加に伴い、チャレンジ層が広がり結果的に受験者数増加に繋がっています。
今回は、そんな新しい中学入試の形式として導入校の増えている「英語入試」と、様々なバリエーションがありながらも求める能力に一貫性の見える「新タイプ入試」についてご紹介致します。
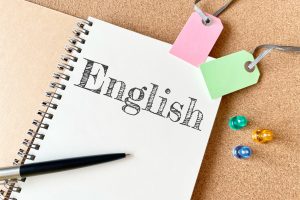
■英語入試
英語入試を取り入れている学校は数年前からありましたが、小学校で英語が教科化された事に伴い、2022年度は英語のみの単独入試を実施する中学が更に増えました。
英語入試は学校により、求められるレベルが様々です。「英検3級程度」等、提示されている目安の英語力に合わせての受験となりますが、今年は特に筆記なしのインタビューや対話形式、グループワークを取り入れる中学校が現れています。
【英語インタビュー型】
…日大豊山女子中学校
(参考:https://president.jp/articles/-/55941?page=2)
レベルは英検3級程度、1人10分程度の英語による口頭試問です。簡単な挨拶と自己紹介の後、短文を30秒で黙読の後音読、さらにそこに書かれた内容についての質問に答える、等を行います。こちらの学校の英語入試の評価ポイントは、リスニングやスピーキングの能力と合わせ「自分の言葉で話せるか」 という点です。たとえ文法的に間違っていたとしても、なんとか自分の考えを伝えようとする姿勢が評価されます。
【英語スピーチ入試】
…目白研心中学校
(参考:https://www.study1.jp/kanto/special/special_report/mejirokenshin3/)
早くから英語に興味を持って英会話を学んでいる児童などが力を発揮できる入試として導入。英語スピーチ入試で入学した生徒や帰国生など、英検準2級以上を持っている子は入学後のカリキュラムでも日本人教員の時間に取り出し授業を行う等、得意な科目を継続的に伸ばしていく体制が整えられています。
【かんたん英語プレゼン入試】
…北鎌倉女子学園中学校
(参考:https://www.study1.jp/kanto/special/dokuji/detail_kitakamakura.html)
こちらの学校が2020年度より導入した「かんたん英語プレゼン入試」は、小6の時点で高い英語力をみるのではなく、英語の能力自体は入学後に伸ばしていくという方針です。試験内容は、提示されたテーマから英語のプレゼンテーションをした後に日本語の質疑応答を行います。他に「エッセイ」や「算数」など、伸びしろも含め、得意分野を活かせる形式の入試を行っています。
上記の学校の例から見えるように、「英語入試」と言っても従来の筆記得点型のものではなく、英語というツールを用いて「特技を活かす」「自分の考えを述べられる」点が評価のポイントとなっています。

■新タイプ入試
この「特技を活かす」「自分の考えを述べられる」という点は「新タイプ入試」で更に顕著に見られる特徴です。4科目以外の能力や資質を見ようとする「新タイプ」入試は、各校が創意工夫を凝らし形式も多岐に渡りますが、その様々なバリエーションの中で共通するのが「思考力」と「主体性」です。
【ポテンシャル入試】
…中村中学校
(参考:https://www.study1.jp/kanto/special/dokuji/detail_nakamura.html)
「ポテンシャル入試」は、教科学習以外でも目標に向かって努力をしている小学生に入学の門戸を広げることを狙いにした入試です。SDGsの1つのゴールを自らのテーマとし、それについて調べたこと、自分の考えを模造紙1枚にまとめプレゼンします。客観的データに基づき自分の考えを説明できるか、という点が評価されます。SDGs視点で課題を研究・発表する形式の入試は他にも導入例があり、今後増加が予想されます。(参考:https://www.study1.jp/kanto/special/dokuji/detail_tokyorissho.html)
【探究サイエンス入試】
…山脇学園中学校
(参考:https://www.study1.jp/kanto/school/B13P132/school_special/2/)
理科(30分)、課題研究(60分)で実施。理科の試験は基礎知識を問う問題で、読解力や計算力なども含めた基本的な学力を見ます。課題研究の試験では、観察から仮説を立てし検証、結果から考察を発表…といった思考プロセスを見られます。解答用紙はポスターで、それまでのプロセスを書いたシートも提出します。2つの試験を通し、学力と探究力の両方が問われる試験形式です。
【プログラミング入試】
…駒込中学校/聖徳学園中学校/大妻嵐山中学校/相模女子大中学部
(参考:https://coeteco.jp/articles/10730)
「Minecraft:入試」「STEM入試」等、実施校により名称は様々ですか、プログラミングを導入する校は年々増加しており、その中にはcrefusコースで使用しているEV3を用いた入試を実施している学校もあります(相模女子大中学部)。また、「Minecraft:入試」を実施している聖徳学園中学校では、プログラミング入試以外にもレゴブロックを用いて考えを立体化、説明する「思考・ものづくり入試」を実施しています。
どの学校のプログラミング入試にも共通しているのは、課題を達成出来たかだけでなく「どのように考えて結果に至ったかを説明できるか」という所も審査される点です。課題を終えた後にはプレゼンテーションがあり、結果やそれに基づく推論、失敗の原因や改善点など、自分の意見を試験官や他の受験生の前で発表します。
■独自の入試多様化の背景にある大学入試改革
このような、スピーチをメインに扱う「英語入試」や独自でありながら思考過程とプレゼン能力を問われる傾向の強い「新タイプ入試」増加の背景にあるのが大学入試改革です。新学習指導要領に記された「主体的に学ぶ力・学んだことを活かそうとする力」を育む為、「知識の量」ではなく「知識を活用する力」を問う入試へと大学入試が変化するのに伴って、高校・中学入試に同様の変化が起こるのは必然です。
たくさんの知識を持つことの価値は恐らく変わらないでしょう。けれど今の子どもたちは、その知識の応用力や、応用した知識を主体的能動的に発信する力がより評価される時代に立っています。主体的、自分で取り組み自分から発信する力は、当然何かの詰め込みや強制で身につく力ではありません。まずは好きだと思えること、夢中になれることから、新しい時代に必要な力の芽を伸ばしましょう。そこから、自分の力でその芽を育てていける力へと繋げていけたら素晴らしいですね。
この記事を書いた先生
-
広島校の佐々木です!
レゴ®ブロックを使って楽しくお勉強するだけで「さんすう」や「りか」も得意になります。友達も誘ってみんなで楽しみましょう!みんなと一緒にお勉強できる日がとても楽しみです。
最近のブログ
- 2024.07.16crefus広島校 crefus シルバーコース「ダンスロボット」
- 2024.06.27crefus広島校 crefus 「交流会」
- 2024.06.21crefus呉校 crefus ブロンズコース 「電動ブレード」
- 2024.06.05crefus広島校 Crefus シルバーコース「ぐるぐるバット君」